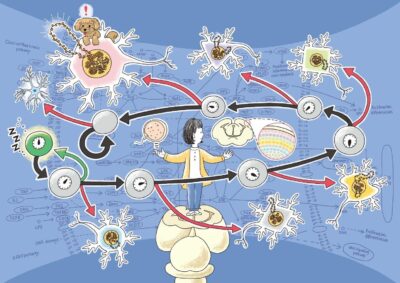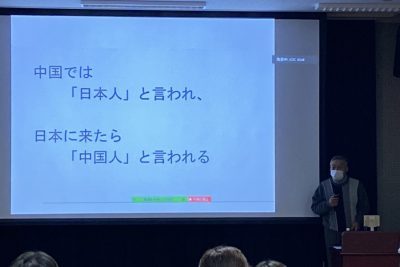日本研究の今後の課題―私論②

※この3篇のブログは、東芝国際交流財団創立30周年記念エッセイコンテストに応募したエッセイを多少加筆したものである。第一篇「日本文化と世界との絡み合い」はこちら。オリジナル版は同財団のウェブサイトに掲載されている。
その二:方法としての日本
ドイツ人として日本史研究をするなかで興味をひかれた点は、視点の変化であった。ドイツにおける歴史教育や国民的議論が、国家社会主義、第二次世界大戦、そしてホロコーストを中心になされているのである。それにはもっともな理由があるのはいうまでもない。1945年以降のドイツ史の目的は、自国の残酷非道な行動を思い起こさせ、それを二度と繰り返さないようにすることであった。近年の世界的な政治動向をみれば、ファシズムの過去を忘れないでいることがあいかわらず重大な課題であることは一目瞭然だが、国家アイデンティティの問題に左右されることなく、外部者として、ある文化に深くかかわれることはやはり新鮮であった。対象との距離ゆえに知的な解放感があり、自分が生まれ育った文化を新たな視点で見ることができるようになる。
ゲイでもある私は、今も昔も日本はヨーロッパとは違うと知るたびに、「なるほど 日本人のセクシュアリティにたいする 考え方は、私の知っているキリスト教圏ヨーロッパのものとは全く異なっていたんだ 」と、大きな衝撃を受けていた。たとえば、日本の武士には男色という習慣があり男性の恋人がいた。性愛を描いた春画は軽妙、滑稽で、近世の大衆文化のひとつであった。歌舞伎ではおおっぴらにエロティックな表現が演じられ、徳川幕府が最初に女性、次に若い男性の出演を禁じる以前は、遊女が歌舞伎を演じることも多かった。こうした事実を知ったことで、私は西洋の価値観や歴史的経験が普遍的なものではないことを理解した。ビクトリア朝の倫理観が明治時代の日本に入ってくると、性に関する道徳観が変わり、同性愛と春画は問題視されるようになった。同時に、「極東」や日本人のセクシュアリティをことさら強調し、エキゾチシズムや人種と結びつけた見方がヨーロッパに広がった。
皮肉にもイギリス人をはじめヨーロッパ人が日本人のセクシュアリティ観を野蛮だと咎めてから150年後の今には、イギリスの学術界は、春画は芸術作品であるという認識を示し、180度見方を転換した。さらに、由緒ある大英博物館が2013年に初めて春画展を開催した。そしてその2年後には日本初の春画展が東京都内の永青文庫で開催された。にもかかわらず近年の欧米メディアの中には日本人のセクシュアリティに対して改めて異国趣味的な報道が増えてきた。たとえば、電車内でアダルト漫画を読んでいる乗客、セックスの回数が減少傾向にある日本人、合成音声の声をもつホログラム「初音ミク」と結婚した男性などが報じられている。一見すると、事実に基づいているようだが、Allison AlexyとEmma E. Cookが近著『Intimate Japan』で指摘しているように、実は「昔からあるステレオタイプを蒸し返したに過ぎない」。
それぞれの国で日本のことを語り、先入観や誤った情報を正し、願わくは理解の促進に寄与することは外国人日本研究者に絶えず求められる任務のひとつである。私は個人的な会話の中で、日本では本を最後のページから読むというのは本当かとよく聞かれる。私の答えは、「普通に考えてみれば、終わりから読み始めると何が何だかわけがわかりませんよね。でも日本では多くの本は右から左に読まれるんです」というものだ。何が普通かという思い込みを崩せればと思っている私であるが、そう答えられる相手がドン引きしてしまうのも当然かもしれない。そもそも、学生や友人、そして関心のある一般市民に対する日本研究者の役割は思い上がりに過ぎず、同時に不十分であるとたまに感じてしまう。
思い上がりだというのは、百年以上たっても、日本文化の何が良くて何が悪いのか、何が時代遅れか何が先進的かの裁定役を、結局は欧米人が果たそうとしているからだ。日本社会はこうした検証をもう必要としていない。たとえ善意であったとしても、こうした役割は学問の上では健全とは思えない。会議の休憩に欧米の研究者と雑話した時、自分の研究のために日本語文献を引用し、活かしながらも、日本語による研究成果を見下げる発言を一度ならず耳にしたことがある。根拠や説明、推論が英語圏研究者の期待と必ずしも一致しないからだ。このような状況では、研究者は開かれた学術交流と知的協力に向けていっそう努力すべきだと、私は強く思う。
2019年の春、東京滞在中に二つの小規模な展示を観にいった。どちらも、日本の友人が勧めてくれなかったら私の目に留まらなかったであろうことを強調しておきたい。ひとつは、銀座のシャネル・ネクサス・ホールで開催された「ピエール セルネ&春画展」だ。浦上蒼穹堂が所有する春画とフランス人アーティスト、ピエール・セルネの抽象的でエロティックな写真作品が展示され、性愛のビジュアル表現について好奇心をかき立てる優雅な対話空間が生まれていた。もう一つは、これとは関係ないがテーマの似た展示で、同じ通りの二ブロック先にあるビルの地下二階の小さな画廊で開催された。テーマは「日本のゲイ・エロティック・アート」で、現代の日本で最も影響力のあるゲイ・アーティストの一人、田亀源五郎のキュレートによるものである。
美しい顔立ちと引き締まった肉体がつくりだすさまざまな官能表現が今や芸術に昇華され、当初意図した鑑賞者とは異なる鑑賞者に向けて展示されており、私はそれらを見て、レズビアンのアメリカ人女優エレン・ペイジによるドキュメンタリーシリーズ「ゲイケーション」を思い出した。ペイジが世界各地を訪れて、その地のセクシュアル・マイノリティの文化を紹介する番組だ。欧米の活動家は、日本のLGBTQの権利保障はほとんど進展していないとよくこぼすが、東京のゲイタウン「新宿二丁目」でインタビューされた年配のゲイ男性の言葉はペイジを驚かせていた。彼は、数十年前の東京のゲイライフに比べて今のほうがよいとは思わない、昔のほうが「千倍素敵」だったと語っていた。
日本国内の多数のゲイやトランスジェンダーの人たちが今現在困難を抱えていることは否定できない。同時に、アメリカや西ヨーロッパの少なからぬゲイ活動家やクィア理論家が同姓婚がもたらしたものに落胆していることを考えると(同性婚が認められたことでさらなる政治的進展が阻害され、主流派からの受容と引き換えにラディカルな生き方が犠牲になったという点において)、地下二階の小さな展示室をまわりながら、海外で日本研究に従事する者は日本人の考え方や経験にさらに真剣に耳を傾ける余地がまだあると感じた。
私はここで、欧米の普遍主義か日本の自国民中心主義かという誤った選択について議論しているつもりではないし、マイノリティを苦しめる社会規範や政策を軽視しようとしているわけでもない。そうではなく、私が強調したいのは、陳光興という研究者の言葉を借りるならば、日本を方法として使うということだ。もう一度鎖国の話に戻るが、日本の経験を知的手段として活用する方法を示した注目すべき研究の一例には、川勝平太の『「鎖国」と資本主義』がある。川勝は、日本の「鎖国」は特異な歴史的現象だという見方を放棄し、日本とイギリスを、一つの連続体の両端、対外関係形成の二つのモデルとしている。そしてこうした観点から、両国のモデルが資本主義の発展に及ぼした異なる影響を再考している。
繰り返しになるが、学術制度のありよう次第でこうした対話が促進されたり、妨げられたりする。地域研究の枠を超えたいという意志をしめす日本研究者の協力も前提となるが、同様に西洋哲学や政治学、フランス文学の研究者は、日本研究者を「非ヨーロッパ」専門家としてお飾りとして扱うのではなく、きちんと耳を傾けるべきである。一方、日本では、英語による日本研究プログラムはいまだに制度上、学部や学科が別扱いされることが多い。正規の教員ポストとなると、日本の大学教員市場は往々にして外国人を締め出す傾向がまだあり、本来日本研究を専門としているのに日本の大学ではやむを得ず英語学科やドイツ語学科などで教えている同僚も少なからずいる。
「その三:教室から考えなおす日本研究」はこちら。
リンク元:RRice